
伊達家御用達の木材を提供していた南三陸。
南三陸で300年続く株式会社佐久を経営している佐藤久一郎様のコーディネートで、森を歩きました🎄

あ!朱色の祠なのかな?
まわりに木が茂っていていかにも神様が住んでいそうだよ。


案内してくれた佐藤さんの説明によると「鎮守の森」についてwikipedia(ウィキペディア)やAIを調べても、どこにも納得する説明が出てこないそうです。

佐藤さんが言うには
「縄文時代の記録にある通り、日本の国土はむかし森でした。
最近よく熊が出た、猪が出たと話題にのぼるが時を遡れば、我々は森に住んでいる狩猟民族だった。」
ん僕もそう習ったよ。

私たち人間は、森をお借りして寝泊まりして木の実を食べ、時にご馳走として自分の身を危険にさらし、命を頂戴していたのですよね。
食べ物がなくて飢えることも多かったから、森を伐って、計画的にいろんな食べ物を育てるようになりました。

水をひく、道を作る、農地を作る!
どんどん自然を自分達にんげんの都合の良いように 作り替えていきました。
その時、先祖様達はそこにある森の一部を残し、生態系を保存し「鎮守の森」とした!

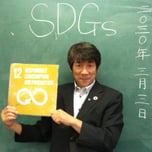
「鎮守の森」であることを示すために祠を建て祀ったと、ほとんどの書に「神社の回りに森を作った」と書いてあります。
でも、ちゃんと考えれば森が先か、神社が先か見えてきますよね。
それだけ自然は尊いものだとつくづく思います。
